
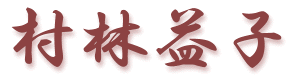

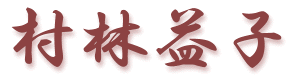
大きな志を持って
二十一年十二月に八十四才になりました。丸紅の設立50周年記念事業として、豊臣秀吉の側室、淀君が召したとされる四〇〇年前の小袖が復元、公開されましたが、その小袖を私共が縫わせて頂きましてから、二十二年一月八日が十年目と新聞にのり、年月の経つ早さに驚きました。
京都の吉岡幸雄先生のご紹介で、山口智子さんが訪問されてから四年を経ました。着方を熱心に学ばれ、今では海外で帯まで締められるようになられました。
二十一年十二月二十四日、テレビ番組で「メンデルスゾーン生誕二〇〇年記念特別番組に山口智子さんが、取材、編集をされ、放映されました。すばらしい番組でしたので、再放送を希望しております。
足の悪い私にやさしく接して下さり、お仕事には誠心誠意取り組んでおられる姿には教えられることが多いのです。
私の寺子屋教室では各地からの熱心な門下生が学ばれ、夜間部には昼間働いてつかれた中を、通って来られ、和裁だけではない大切な常識の学びを喜んでくれているようです。
さて私の残る人生に大切なしとげなければならない大仕事があります。
日本の大切なきものの道を正しく後世に残して行く道なのですが、実は理解しようと真面目に方法を考えて下さる方が集って下されば、ごく簡単に説明がつくことなのです。しかしよほど哲学のある方でないと、「本当に正そう」と思って下さらないでしょう。
次の私の拙い説明でおわかり下さる方がいらして下さるでしょうか。お願いいたします。
和裁の道ははっきり二通りに分かれています。第一は専門家(つまり仕立を本職にしている、高級仕立ての出来る人たち)
一方は学校教育で和裁を教えるという目的で、小学校から黒板で説明するよう教えられてきた学校式和裁があります。
困ったことに専門家はお料理と同じように昔は、学校の先生方には本物の和裁は教えることなく、又教科書も作りませんでした。
学校教育を志す先生方は苦心なさって、教科書を作って来られたのです。
しかしそれが弊害があった事に。今も弊害が残っている事に、「日本の和裁」の道は気付かないでまいりましたし、気付かない知られない、とても残念なことであります。
他の学問や医学でしたら多くの男性が、研究され、良し悪しは理解お出来になるでしょうが、この和裁の道に関しては理解しようとなさる方も少ないでしょう。
又驚く事に私に多額の金銭を要求し、私を日本一に奉って上げると云われた事が二回もございました。
専門家は職業として日夜仕立物をいたしますので、仕立方は正確で早く簡単に仕立てられる方法です。
一方は裁ち方、縫い方に大きな差があります。布はチャコやひどいものは鉛筆で線が引かれ、専門家の縫い方とは何倍も時間が必要です。ですからお裁縫がきらいな婦人が多くなり、家族のものでさえ縫えなくなってしまいなした。
若い方の間に着物に関心を持って下さる方が多くなって来ました。指を動かすことは健康にも必要な事だそうです。
次々と着やすい着物が出来上がっていくいく喜びで、門下生は長く学んでおります。各地から熱心に
学びたいむねのお手紙が来ますが、遠い方には手をさしのべる事が出来ません。遠い方がせめて身の廻りの方の為に縫い物が出来るように、「国が力を貸して下さらないのはおかしい」と外国の方が不思議
だと云って下さるのです。
討論してくださる方の、哲学を持たれた方の、お目にとまりますように。神を信じて。(平成二十二年一月記)
※平成二十一年五月十日(日)三越劇場の「こけらおとし」に山口智子さんとトークをしました。おかげさまで大好評でした。
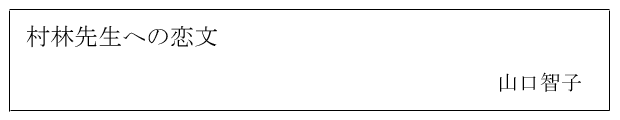
師と仰げるかたと出会えるということは、なんと幸せなことでしょう。
「村林先生のもとで学びたい!」と、心から沸き起こる衝動に駆られ、先生に弟子入りを申し出て数ヶ月、日に日に私の人生が豊かに美しく仕立て直されてゆく感動は、まさに人生の宝。
「着たい“きもの”がどこにもない」
先生とのご縁を結んでくれたのは、どうも馴染みきれない現代のきもの文化でした。日本の四季や風土や歳月に育まれた「きもの」というものに、心から憧れるものの、現実の暮らしの中ではどこか無理があり、気軽に入り込めない高い壁を感じていました。
江戸の錦絵や桃山の屏風絵には、奔放な色気に満ちた着崩し上手の美人がたくさん登場するというのに、今の四角四面の着付けから、どうしたら脱出できるのか? そんなことを考え悶々とする日々でした。
そして遂に運命の出会い。染織家の吉岡幸雄さんが、村林先生をご紹介くださいました。
「とにかく簡単に、楽に、しかも、美しく、色っぽいきものが欲しいのです」。
初対面での無謀な私の我がままを面白がってくださったのか、先生は一週間後、世界のどこにもない美しい浴衣をふたつ、縫い上げてくださったのです。
先生はほんのわずかの時間で、私の体の寸法や特徴を見事に見抜かれて、お端折なしでさらりと羽織れる対丈【ついたけ】の浴衣を、ぴたりと完璧に仕立ててくださいました。
袖を通した途端、愛に包まれるとはこういうことだと心が震えました。
衿を合わせるだけで体の凹凸にぴたりと馴染む仕立ては、纏う者に心地よい緊張感も与えてくれます。騒がしい襞や皺がひとつも存在せず、見えないところにこそ心を込めて、一針一針手をかけられた温もりに満ちていました。
「袖を長くしといたの。優雅でしょ?」
先生のおっしゃる通り、お端折のない「ついたけ」の中性的な魅力に、雅な丸みのある袖が揺れる様は、まるで屏風絵から抜け出てきたよう。
「世の中の着付けは難しすぎる。間違いだらけなのよ。もっと簡単でらくちんでいいの」
きもの本来の自由奔放な独創性と、究極に磨き抜かれた伝えるべき知恵をきちんと世に伝えたい。先生はその熱い思いに駆られ、おかしいと思ったことは改善するべく、いろいろな場所に乗り込まれてゆかれるのだとか。その武勇伝はお茶目で可愛く、いつも笑い転げながらお聞きしては、先生のパワーに恋い焦がれるばかり。きものを愛し、どこへでも突撃し、笑いと幸せ旋風を巻き起こされる村林先生は、眩しいほどに輝いていらっしゃる!
「戦争があったから鍛えられたわ。ありがたい。感謝しなくちゃ。」
「父に扇風機を買ってあげたくて一生懸命働いて、四人の子供たちにご飯食べさせて、いつもいつも誰かのことを想ってやってきたら、なんだかいちばん得しちゃったのは私みたい」
どんな負の状況も、鮮やかにプラスの力に変えてしまう先生は、たくましく潔くお美しい。先生のご著書『ます女きもの手控え』のなかに、大好きな言葉があります。
「見渡せば、有り難いことばかりでございます。」
私は、村林先生のこの言葉とともに、いつか私も世の為に光を放てる人生を目指し、日本を、もっともっと学んでゆきたいと思います。そして、確実に伝えてゆくことを約束します。
先生、これからもご指導、よろしくお願いいたします!
心からの感謝と尊敬を込めて
二〇〇七年の佳き日
山口智子 (やまぐち・ともこ 女優) 筑摩書房 PR誌ちくま 2007年10月号より